消防法
2022.12.22
「消防隊進入口」の基準や役割を徹底解説

ビルの窓に張り付けられている逆三角形の赤いマークを見たことがある人は多いと思います。
あのマークは「消防隊進入口」を示すもので、非常時にはしご車などを使った消防隊が迅速に建物内に進入できる場所を知らせる役割があります。
そんな「消防隊進入口」には様々なルールがあるため、ビル管理者や建物の責任者は消防点検などに備えて知っておくべきことがたくさんです。
この記事では、消防隊進入口についての基準や役割、さらには諸条件について知っておきたいポイントに焦点をあててわかりやすく解説します。
【目次】
1. 消防隊進入口とは
2. 消防隊進入口の基準
3. 消防隊進入口を妨げるとして指定されている物
4. 非常用進入口の設置基準が緩和されるケース
5. 消防隊進入口の設置基準について迷ったら
6. まとめ
1. 消防隊進入口とは
消防隊進入口とは、火災が発生した際に消防隊が建物外部から内部へ進入するためのバルコニーや開口部のことです。
消防隊進入口は「非常用進入口」とも言いますが、いずれも同じ意味として使われており、口語では「消防隊進入口」、建築基準法といった法律上では「非常用進入口」が用いられることが多いようです。
後述しますが、消防隊進入口は「非常用進入口」と「代替進入口」の2種類があり、いずれも消防隊が内部へ進入できる場所という目的や役割は同じです。
消防隊進入口を示すマーク
消防隊進入口を示すマークとして、逆三角形をしたステッカーが貼られており、建物の外側は赤色、建物の内側は白色でなおかつ「消防隊進入口」と記載されています。
これは「消防隊進入口マーク(三角形ラベル)」と呼ばれ、一辺が20センチの正三角形、外側は反射素材で赤色、内側は無反射と規定されています。
消防隊進入口マークは、万が一の火災時であっても、はしご車などを使って消防隊が速やかに内部へ進入できる場所を示すとても重要な役割があります。
消防隊進入口の構造
消防隊進入口は「バルコニー」、「赤色灯」、そして「消防隊進入口マーク」の3つで構成されます。
それぞれ以下のような規定があります。
・バルコニー:長さ4メートル以上、奥行1メートル以上
・赤色灯:直径10センチ以上
・消防隊進入口マーク:一辺が20センチの赤色で反射素材(裏側は白色)
*進入口の大きさは高さ1.2メートル以上、幅75センチ以上
消防隊進入口は厳密には上記のような規定がありますが、すべての建物がこのような条件を満たすことはできません。
そのため、消防隊進入口として代用できる「代替進入口」の設置が認められています。一般的には、消防隊進入口マークは窓に貼ってあると思いますが、これは窓を「代替進入口」として使用していることが背景にあるのです。
つまり、日頃から多くの人がビルを眺めた際に目にしているであろう消防隊進入口は「代替進入口」であると思ってよいでしょう。
代替進入口の構造
代替進入口は、直径1メートルの円が内接、または幅75センチ以上および高さ1.2メートル以上の窓、その他の開口部を、幅員4メートル以上の道または通路に設けることという規定があります。
多くの場合、大きな窓を取り付けることで上記の条件を満たせることから、窓を代替進入口として使用している訳です。
代替進入口の場合であっても、赤色灯や消防隊進入口マークを付けなければいけません。しかし、各市町村の条例によって消防隊進入口マークだけでよいとする場合もあるため、あらかじめ行政担当者に確認する必要があります。
消防隊進入口を規定する法律
消防隊進入口は消防法によって定められていると思われがちですが、実際は「建築基準法」で規定されています。
消防隊進入口については、建築基準法による規定のため消防点検の際に指摘または指導されることはないと思う人もいるようです。
しかし、消防法第7条に基づく消防同意事務等取扱規程の「同意の審査」によって「消防活動についての規定に適合しているかどうか審査」とあることから、規定に従っていないと指導を受けることになります。
参考:建築基準法施行令 第五節 非常用の進入口、消防法第7条に基づく消防同意事務等取扱規程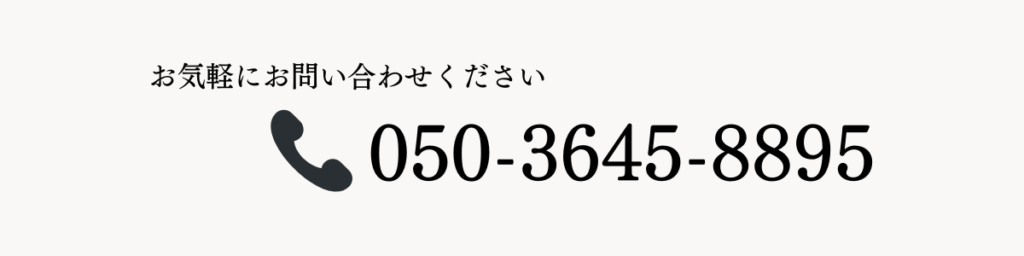
2. 消防隊進入口の基準
次に、消防隊進入口つまりは非常用進入口を設置する際の基準について解説します。
高さ
消防隊進入口を設置する高さの基準は「31メートル以下の部分にある3階以上の各階」です。
“建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。”
通路幅および開口部
消防隊進入口で規定されている幅員の基準は「4メートル」です。
“道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合”
設置間隔
消防隊進入口を設置する間隔は「40メートル以下」です。ただし、福岡市のように「40メートル以下かつ端から20メートル以内」とより詳細に定めている場合もあるため、各自治体の条例を確認するようにしてください。
“進入口の間隔は、四十メートル以下であること。”
代替進入口の設置基準
代替進入口の設置基準は「設置の間隔が狭くなる」ことが特徴です。代替進入口は「10メートル以内」の間隔で設置しなければいけません。
つまり、大きなビルほど代替進入口ばかりになることから「非常用進入口(バルコニー)」を設置するようになる訳です。
3. 消防隊進入口を妨げるとして指定されている物
消防隊進入口は建物の外側から進入しやすくするだけでなく、建物の内側においても気を付けなければいけないことがあります。
とりわけ、注意したいことが「進入を妨げる障害物」です。これらの障害物についても規定があるため、覚えておきましょう。
・外部から解放不可能なドア
・金属製格子および手すり
・ルーバー
・窓を覆うように設置してある看板やネオンサイン等
上記に該当するような物が設置してある場合は、消防点検の際に指摘される可能性があります。
また、消防隊進入口の内側に段ボールや商品が積み重ねてあるケースも多く見られることから、注意しましょう。
ちなみに、建築基準法で進入口の構造を規定する内容として「進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。」とあります。
具体的な素材等は規定されていないものの、上記の条件を満たす構造であれば問題ないと考えられています。
従って、網入り窓は不可、店名などが記載されたサインフィルム等は可、といった解釈が一般的です。
4. 非常用進入口の設置基準が緩和されるケース
非常用進入口の設置基準には緩和されるケースがあるので覚えておくと役立ちます。
代替進入口を設置している
先述したように、非常用進入口(バルコニー)は、必ずしもすべてのビルが設置できる構造とは限りません。
そのため、非常用進入口の代わりとなる「代替進入口」があれば、非常用進入口を設置しなくてよいという緩和措置が取られています。
火災が発生する恐れが少ない階
火災が発生しにくい階については、対象階の上下階に進入口を設ければ非常用進入口を設置しなくてもよいという緩和措置があります。
火災が発生しにくい階の定義としては「不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階」と定められています。
具体的な例がないため解釈が曖昧になりがちです。前もって消防署や行政と確認することをおすすめします。
進入を防止する必要がある階
外部からの進入を防ぐ必要がある階の場合も非常用進入口の設置が緩和されます。具体的には、放射性物質や有毒ガスなどと取り扱う建築物、細菌や病原菌を取り扱う建築物、爆発物を取り扱う建築物、発電所、美術品収蔵庫、金庫室などが該当します。
これらがある階にこそ非常用進入口の設置は必要ありませんが、上下階には非常用進入口を設置しなければいけないことを忘れないでください。
“国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。”
5. 消防隊進入口の設置基準について迷ったら
消防隊進入口や非常用進入口の設置基準については建築基準法だけでなく市町村ごとに異なる条例も考慮しなければいけないため、一概に規定がすべての建物にあてはまるとは限りません。
そのため、消防隊進入口については管轄の消防署と行政、そして建築主事(建築士)に相談するようにしましょう。
6. まとめ
消防隊進入口は万が一の時に消防隊が外部から内部へ進入するための非常に重要な規定です。また、消防隊進入口については詳細な規定や緩和措置があり、市区町村ごとの条例も加わることから複雑になってしまいます。
消防点検の際に指導を受けないようにするためにも、日頃から消防隊進入口の周辺には物を置かないようにすることや、その役割を徹底周知するように努めましょう。
消防設備点検なら全国消防点検.comまで

全国消防点検.comでは消防設備点検のご相談を承っております。
「古い建物でいつ設置されたものかわからない・・・」
「消防設備についてよくわからないし、点検もしているのかな?」
などなど、些細なことでもご相談を承っております。
消防点検に限らず、様々な設置や点検等も承っており、
依頼する業者をまとめたい、点検類をまとめて依頼したいなど幅広くご相談が可能です
まずはご相談だけでも大歓迎です!
どうぞお気軽にお問い合わせください。


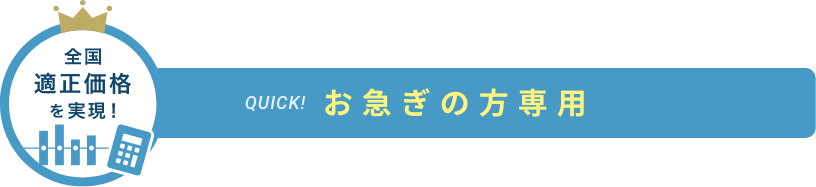

 スプリンクラーのアラーム弁とは?設置基準や点検方法を解説
スプリンクラーのアラーム弁とは?設置基準や点検方法を解説