消防法
2022.12.22
消防法における「無窓階」とは?定義や判定を解説

消防法や消防点検などの際、頻繁に「無窓階(むそうかい)」という言葉に触れる機会があると思います。
無窓階は読んで字のごとく「窓がないフロア」と考えてしまいがちですが、消防法における無窓階の意味は単純ではありません。
また、消防点検の際には無窓階について指導を受けることもよくあるため、しっかりと定義や判定基準を把握しておくことが大切です。
この記事では、消防法における無窓階について、重要なポイントを初心者にもわかりやすく解説します。
【目次】
1. 無窓階の定義
2. 消防無窓だとどうなるのか?
3. 無窓階の判定
4. 開口部の構造
5. 無窓階の判断に迷ったら
6. まとめ
1. 無窓階の定義
「無窓階」とは、消防法施行規則で定められている避難上または消火活動上において有効な開口部を有しない階のことです。
ごく簡単に言えば、避難や救助の際に利用できる開口部が存在しない階となります。開口部については後述しますが、建築基準法において原則として高さ1.2メートル以上、幅75センチ以上、そして外部から容易に破壊できる構造が求められています。
つまり、建物に窓があったとしても、開口部が基準を満たしていなければ一律に無窓階と判定されてしまう訳です。
消防法における無窓階とは、窓の有無ではなく、あくまでも「避難や進入に有効な開口部があるかどうか」がポイントになることを覚えておきましょう。
無窓階と普通階の違い
消防法における「無窓階」と「普通階(有窓階)」の違いは、避難や進入に有効な開口部があるかどうかです。
また、建築基準法によって定められている開口部の設置基準(材質等も含む)を満たしているかどうかも問われます。(開口部の基準は消防法ではなく、建築基準法で規定されている)
有効な開口部がなければ無窓階、有効な開口部があれば有窓階と判定されます。ちなみに、建築基準法では「無窓居室」や「無窓」といった言葉が用いられますが、消防法の無窓階とは定義が異なります。
建築基準法では、採光のための窓の有無であったり、大きさであったりが基準ですが、消防法では開口部の有無です。
無窓階と地下階との違い
消防法において地下は無窓階として扱われず、代わりに「地下階」として別の基準が適用されます。
消防法では、地下階と無窓階は別物の扱いになることと、普通階と比較してそれぞれ消防設備の設置基準が厳しくなることを知っておくとよいでしょう。
消防設備の設置基準が厳しくなるということは、それだけ消防設備に対するコストも増大することも合わせて覚えておいてください。
2. 消防無窓だとどうなるのか?
消防点検等により無窓階と判定された場合、以下のような影響が生じます。
・避難や消防隊の進入が容易でないため危険
・消防設備の設置基準が厳しくなる
・消防設備導入コストの負担が増える
無窓階と判定された場合、当然ながら避難や消防隊による救助が難しくなるため、万が一の火災時による被害が大きくなる可能性があります。
また、無窓階での被害を最小限に留めるために消防設備の設置基準が厳しくなり、普通階であれば設置しなくてよい設備を、無窓階であることを理由に設置しなければいけなくなります。
このことは、有窓階であればコストがかからないところ、無窓階であるが故にコストがかかることを意味します。
具体的には、普通階であれば低コストで設置できる「熱感知器」を主体にして警戒できますが、無窓階だとより早く火災を検出できるものの高コストな「煙感知器」を主体にしなければいけません。
一般的に、煙感知器は熱感知器と比較して4倍程度の価格差があるとされていますので、無窓階だとコストがかさむことは否めません。
また、対象の建物の用途が劇場や遊技場、百貨店などの場合は、大がかりな消防排煙設備の設置が義務付けられます。
3. 無窓階の判定
無窓階か否かについては消防法によって判定基準が定められています。
以下の条文を要約すると「建物の11階以上と、10階以下で判定基準が異なる」ことが分かります。
“令第十条第一項第五号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。”
以上を踏まえると、無窓階か普通階かを判定する基準は以下のようになります。
・11階以上:直径50センチ以上の円が内接できる開口部との面積の合計が1/30以下
・10階以下:直径1メートル以上の円が内接できる開口部、または幅75センチ以上高さ1.2メートル以上の開口部を2つ以上有し、かつ直径50センチ以上の円が内接できる開口部との面積の合計が1/30以下
引用:消防法施行規則 第五条の三
4. 開口部の構造
消防において無窓階か有窓階の判定については「開口部」が肝になると言えます。開口部の設置や構造についても理解しておきましょう。
開口部の設置位置
無窓階の判定基準には「開口部の設置位置」もあります。
以下で紹介する消防法の条文を要約すると「開口部は、開口部の下端が床面より1.2メートル以内で、なおかつ開口部がある面は幅1メートル以上の通路や空き地に面していること」となります。
“前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
一 床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
二 開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
三 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
四 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。”
開口部の設置位置については、消防隊が円滑に進入できることを考慮しています。開口部が高すぎる位置にあったり、路面に面していなかったりすると意味がありません。
ちなみに、開口部の大きさは「消防隊がボンベ等の装備を背負った状態で建物の内部へ進入できる」ことを想定しています。
開口部の素材
消防における無窓階について注意すべき点として「開口部の素材」が挙げられます。
例えば、開口部の建具として「網入りガラス窓」が設置してある場合は、条文が示す「容易に破壊することにより進入できるものであること」を満たせないため、無窓階の判定を受けてしまいます。
また、防音効果を高めるためにガラス厚が10ミリ以上ある物を使っている場合、消防隊が外部から破壊するための作業場(バルコニー等)がなければ開口部として認められません。
一方で、施錠された鉄製の扉(容易に破壊できない物)であっても、ガラス製の小窓が付いており、内側のサムターンに手が届くような場合は開口部として認められます。
開口部の素材については一概に規定が当てはまらないことから、所轄の消防署による判断を仰ぐしかありません。
仮に、ビル改修工事等で開口部を変更するようなことがある場合は、あらかじめ所轄の消防署に相談したうえで手を加えるようにしましょう。
ガラスの構造
消防の無窓階については「開口部の素材」も重要ということが分かったと思いますが、とりわけ「ガラスの構造」についてはよく理解しておいた方がよいでしょう。
開口部の基準を定めた条文には「容易に破壊することにより進入できるものであること」とありますが、ガラスの場合は「厚さ6ミリ」がその基準とされています。
ただし、各市区町村によって条例等が異なることから、あくまでも目安として「ガラスは6ミリ厚」と覚えておきましょう。
以下の表では「開口部の基準を満たすガラスの種類と厚み」をまとめます。
| ガラス開口部の種類 | 厚み |
| 普通板ガラス フロート板ガラス 磨き板ガラス 型板ガラス 熱線吸収板ガラス 熱線反射ガラス | 8ミリ以下 *厚さが6ミリを超えるものは,ガラスの大きさが概ね2㎡以下かつガラスの天端の高さが、設置されている階の床から2m以下のものに限る。 |
| 強化ガラス 耐熱板ガラス | 5ミリ以下 |
この他の、鉄線入りガラスや網入りガラス、合わせガラスなどについては、原則として開口部の基準を満たせないと思ってよいでしょう。
5. 無窓階の判断に迷ったら
消防の無窓階の判定に迷った場合は、必ず所轄の消防署や行政に相談するようにしましょう。
インターネット上にある無窓階に関する情報が必ずしもあなたの建物に該当するとは限りません。また、建物の構造や用途によって設置しなければいけない消防設備も変わってくるため、注意しましょう。
お住まいの地域によっては、この記事でご紹介した内容とは異なる条例が適用されるケースもあるため、無窓階の判定を巡る詳細ついては消防署や行政とすり合わせるようにしてください。
6. まとめ
消防の無窓階については「開口部」のことを理解することが大切であることが分かったと思います。
また、開口部の基準として「設置位置」や「素材」、「大きさ」など様々な規定があることから複雑化してしまいます。
無窓階か普通階かの判定については管轄の消防署が消防点検の一環として判断しますので、消防点検の際に指導を受けないよう改めて無窓階の基準や用途を確認することをおすすめします。
消防設備点検なら全国消防点検.comまで

全国消防点検.comでは消防設備点検のご相談を承っております。
「古い建物でいつ設置されたものかわからない・・・」
「消防設備についてよくわからないし、点検もしているのかな?」
などなど、些細なことでもご相談を承っております。
消防点検に限らず、様々な設置や点検等も承っており、
依頼する業者をまとめたい、点検類をまとめて依頼したいなど幅広くご相談が可能です
まずはご相談だけでも大歓迎です!
どうぞお気軽にお問い合わせください。


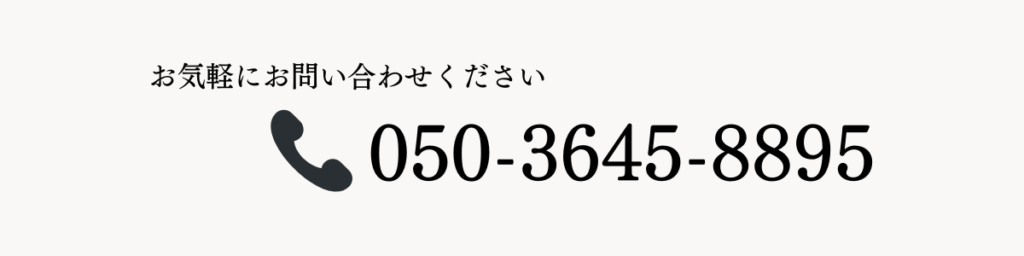
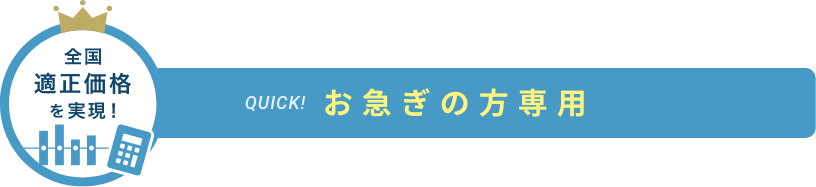

 「消防隊進入口」の基準や役割を徹底解説
「消防隊進入口」の基準や役割を徹底解説