消防法
2023.04.16
飲食店の消火器設置の義務化について【消火器の種類と設置基準】

2019年10月〜法改正で飲食店に消火器が必要に

「ここ最近、街中や建物の中で消火器を見かけること多くなったなあ。」
と感じる方いらっしゃいませんか?
実はそれ、勘違いではありません!!
消火器設置基準に関する法改正が行われ、2019年10月から新しい消火器設置基準が設けられています。
飲食店の消火器設置基準

改定内容
過去には、延べ面積が150㎡以下の飲食店には消火器を設置する必要はありませんでした。
しかし、2019年10月からの法改正により、消火器の設置が基本的に必要となりました。この要件は、延べ床面積に関係なく適用されます。
ただし、例外的にガスコンロなどの火を使用しない飲食店やIHのみの場合には、消火器の設置義務はありません。
また、火を使用する器具がある場合でも、防火上有効な措置がある場合には、消火器の設置義務はなくなります。
これらの措置には、
・調理油過熱防止装置
・圧力感知安全装置の安全機能
・自動消火装置
などがあります。
しかし、このような設備がある飲食店はあまりないため、ほぼすべての飲食店で消火器の設置が必要です。
また、消火器はガスコンロなどがある階にのみ設置すればよく、火元となり得る箇所から歩行距離20m以内に設置する必要があります。
飲食店に設置する消火器の種類

消火器のサイズについて
| 店の面積 | 消火器の種類 |
| 100㎡未満 | 強化液消火器の3型以上 |
| 100㎡以上 | 強化液消火器の6型以上 |
店の面積が100㎡未満の場合は粉末消火器もしくは強化液消火器の3型以上、
100㎡以上の場合は粉末消火器もしくは強化液消火器の6型以上を設置する必要があります。
住宅用消火器は認められません。
消火器の適切な設置場所

店の各階ごとに、どの場所からも歩行距離20メートルで消火器に至ることができるように設置し、
1本で届かない場合は複数本設置する必要があります。
また、通行又は避難に支障がなく、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置します。
「消火器」の標識は床面からの高さ1.5m以下に設置し、見やすい位置に付けましょう。
そのほか、消火器に表示されている「使用温度範囲」内の場所に設置する必要があります。
地震や振動で消火器が転倒、落下せず、消火薬剤が凍結、変質又は噴出するおそれの少ない場所に設置します。。
高温・多湿場所も避けることが必要です。
高温や湿気の多い場所、日光・潮風・雨・風雪等に直接さらされる場所、腐食ガスの発生する場所(化学工場、温泉地帯等)などに設置する場合は、格納箱に収納するなどの防護を行いましょう。
また、厨房室での床面、作業場の地面等への直置きは避け、壁掛け又は設置台、格納箱に設置します。
また、6か月に1回以上は外形を点検することが義務付けられています。
飲食店は特定防火対象物になるため、1年に一度消防署への報告が必要になります。
ご自身で点検をされる方は注意しましょう。
※全国消防点検.comでは消防設備点検を消防設備点検から行政への報告まで、国家資格を有するスタッフが責任を持って実施・代行しています。
有識者の必要な消防設備点検は、全国消防点検.comまでお問い合わせください。
飲食店に適切な消火器をご案内!
これはズバリ言えば
機械泡消火器
強化液消火器

機械泡消火器

強化液消火器
の二つです。どちらも油火災に対して非常に有効なんですね!粉末消火器は油火災に対応していないわけではないのですが、引火した油が飛び散る可能性もあるため、上記二つの消火器と比べると油火災に対しては弱いんですね。
粉末消火器と強化液消火器を比較した実験映像があるので、こちらを見てもらうと油火災に対する消火能力の違いが一目瞭然かと思います。
どちらも油火災が発生しやすい飲食店にはおすすめの消火器です。消火薬剤以外の粉末消火器との違いはホース先のノズルに特徴があることです。
機械泡消火器や強化液消火器のお求め・ご相談はお気軽に全国消防点検.comまでご連絡ください!!
飲食店の消防設備なら全国消防点検.comにおまかせください!

今回は消火器の種類と設置基準を中心にご紹介しました!
2019年10月からは飲食店の消火器設置基準が変わり、基本的に延べ床面積に関わらず消火器の設置が必要となっています。
消火器のお求め・ご相談はお気軽に全国消防点検.comまでご連絡ください!


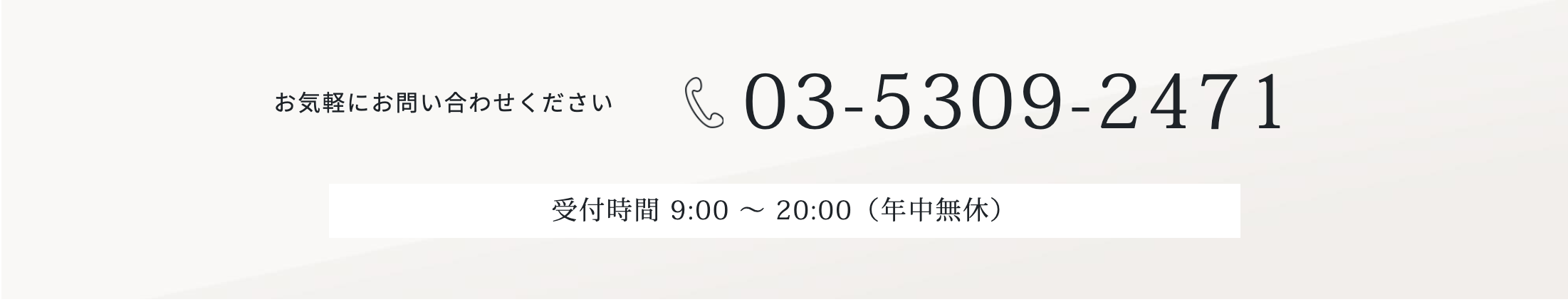
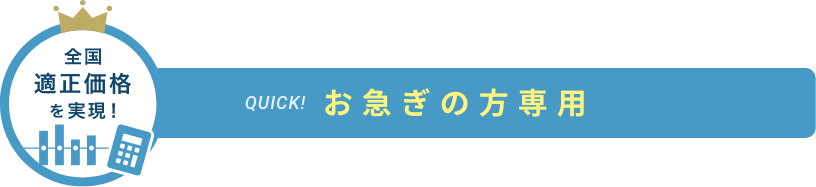

 【 トマホークジェット 】徹底解説!飲食店向け自動消火装置
【 トマホークジェット 】徹底解説!飲食店向け自動消火装置