消防用設備
2022.11.28
今さら聞けない消火栓のあれやこれ

消火栓とは、消火活動に必要な水を供給する為の設備。
自動で放水されるスプリンクラーなどとは異なり、人力での消火活動を想定しているものです。
屋外型は街中に配備されており、マンホールのように地面に蓋がついているものを見たことがあるかもしれません。
また、屋内型も会社の廊下やショッピング施設などに設置されているので、普段から気づかずに目にしていることでしょう。
そんな消火栓ですが、実は一般人でも使用可能です。
今回はそんな消火栓の構造について詳しくなるとともに、何かあったときのために使い方もマスターしておきましょう。
【目次】
1. 消火栓の種類
2. 消火栓の使用方法
3. 消火栓はどこに設置するの?
4. まとめ
1. 消火栓の種類
消火栓には屋内型と屋外型の2種類があり、見た目や使い方が異なります。
屋内消火栓の種類
屋内消火栓は火災の初期消火を目的としていて、扱いやすさや消火性能の違いから3種類あります。
1号消火栓
昔から使われているのがこちらの1号消火栓ですが、利便性も高くなく、ホースをすべて引き出さないと放水できないため、最低でも2名以上で操作しなければいけません。
しかし消火能力は高く、設置できる防火対象物も限定されません。
利便性がない代わりに非常に強力な消火設備です。
平たいホースが縦に蛇腹状に折りたたまれて収納されています。
高い消火能力を有しているため工場や倉庫などでも使用可能で、ホースも長いので消火栓を設置する数も少なく済ませることが可能です。
易操作性1号消火栓
易操作性1号消火栓は1号消火栓と同じ条件の場所に設置が可能で、性能も1号消火栓と同じです。
しかも取り扱いが比較的カンタンで、一人でも操作できるといういいとこ取りの優れもの。
それならすべての1号消火栓を取り替えればいいのでは?となりますが、易操作性1号消火栓へ改修する場合、ポンプの増強と消火栓箱を大型に変更する必要があります。
2号消火栓
2号消火栓は1人でも扱いやすいように設計されたものですが、1号消火栓よりも放水量が限定され、設置できる防火対象物も限られてきます。
1号消火栓よりも性能が劣るため、消火栓の設置個数も比較的多くなります。
屋外消火栓の種類
屋外消火栓は文字通り屋外に設置されている消火栓です。
建物の周囲に設置され、建築物の1階と2階の消火活動を目的としてしています。
必要なものがすべて入っている器具格納式消火栓と、ホース格納箱を付近に配置しなければいけない地下式・地上式消火栓の3種類があります。
地下式
マンホールのように地面に『消火栓』などと書いてあるフタを見たことはありませんか?
そのフタの下にあるのが地下式の消火栓です。
フタを開ければ使えるわけではなく、近くにあるホース格納箱からホースや必要器具を持ち出し、接続することで消火活動がはじめられます。
普段気にしていないだけで、実はそこら中にあるんです。
地上式
まちなかではあまり見かけることはありませんが、おそらく消火栓の皆さんのイメージに一番近いものが地上式のものです。
これはその名の通り地上に露出しているタイプで、ヒザ下ぐらいの高さで赤いポール状なのが特徴です。
地下式と同じく、単体では消火活動ができないので後述するホース格納箱からホースや必要器具を取り出し、接続して使用する必要があります。
ホース格納箱
ホース格納箱だけでは消火活動ができませんが、地下式と地上式を利用した消火活動には必須のアイテムです。
地下式・地上式消火栓の歩行距離5m以内に設置されていて、消火栓につなぐホースやバルブを回すための器具などが入っています。
器具格納式消火栓
操作方法や見た目も屋内型消火栓と似ていて、だいたい建物の外壁にくっついています。
消火栓の構造
消火栓の構造は基本的に屋内型、屋外型で違いはありません。
屋内消火栓には水源、加圧送水装置、ホースやノズルが収納されている消火栓箱、これらを連結する配管、そしてポンプを始動させる起動スイッチや表示灯が一般的に含まれています。
火災が発生し、消火栓のボタンが押されます。
すると消火栓ポンプが起動。
地下などにある貯水槽を水源として、加圧送水ポンプにより各消火栓に送水開始。
消火栓の開閉バルブを開栓すると現場で放水ができます。
屋外型消火栓も同様の構造ですが、消火栓とホースが別になっているので、
ボタンを押すだけでは送水が開始されません。
スタンドパイプと差し込んだり、ホースを接続したりすることでようやく放水が可能になります。
2. 消火栓の使用方法
消火栓は適切な方法で使用しないと満足な消火活動ができないばかりか、怪我をしてしまうことも。
二次被害を生まないためにも適切な方法を学んでおきましょう。
またここで紹介するのはあくまで一例なので、普段通勤している会社やよく利用している施設のものはどんな構造なのかしっかりと把握することが大事です。
屋内消火栓
1号消火栓
1号消火栓はホースをすべて引き出さないと放水ができません。
放水のためのバルブが消火栓ボックスについているため、必ず2人以上で操作してください。
1.発信機のボタンを押すとポンプが作動、表示灯が点滅しベルが鳴動していればOKです。
2.ノズルを持ち、ホースを最後まで伸ばし放水体勢をとる。
3.開閉弁を開いて放水開始。
易操作性1号消火栓・2号消火栓
名前の通り、従来の1号消火栓から操作を簡易化したものが易操作性1号消火栓。
従来の1号消火栓から放水量を減らして扱いやすくなっているのが2号消火栓です。
どちらも1人での操作が可能です。
1.開閉弁を開放するとポンプが始動、表示灯が点滅しベルが鳴動していればOK。
2.適切な長さまでノズルを持ち、ホースを伸ばしてノズルについている開閉装置を開放して放水開始。
屋外消火栓
屋外消火栓はひとりでは使用できません。
そのため万が一火災を発見した場合は最低でも3人以上で消火活動に当たってください。
まずはホース格納箱からそれぞれ器具を取り出しておきます。
地下式
1.専用ハンドルをフタについている穴に差し込み開けます。
2.消火栓のふたを開けて消火栓ハンドルを差し込む。
3.ホースを延ばし、筒先とホースのオス金具を結合します。
このとき、ホースにねじれや折れがないようにしっかりと伸ばしてください。
放水時の水圧は非常に高く、ねじれがあると怪我をしたり、適切な水量が現場に届かないこともあります。
そのため、しっかりとホースを伸ばしきったことを確認してから放水を開始してください。
また、延長のしすぎでケガなどをしないように、本当にホースの延長が必要かどうかも確認しましょう。
4.バルブ操作員は、合図し、バルブを左に回し全開にする
バルブ捜査員はホースの担当者からねじれや折れがないかの合図を受け取り次第、放水するためのバルブを回します。
水を出すのは筒先担当者がしっかりとスタンバイできてから。
先に水を出してしまうと水圧で怪我をしてしまう可能性もありますので十分に注意してください。
地上式
1.開ける
側面にある黒い蓋を左に回して外します。
2.差し込む
消火栓の上部にあるフタを開けて消火栓ハンドルを差し込みます。
3.以降地下式と同様
あとは地下式と同じようにホースを接続して各担当から合図を受け取り次第、放水担当者が放水を開始します。
放水する位置は屋外の足場がしっかりしていて安全が確認できている場所にしましょう。
放水が開始されると手元にかなりの衝撃が来ます。驚いて落としたりしないように十分に注意してください。
3. 消火栓はどこに設置するの?
火災を最小限に防ぐためには重要な消火栓ですが、いったいどのような設置基準があるのでしょうか。
屋内消火栓の場合
そもそも屋内消火栓を設置しなければいけないかどうかですが、屋内消火栓の設置は建物の構造と面積の組み合わせによって決まります。建物を3つのタイプに分けて、そのタイプごとに設定されている面積より大きいかどうかで判定。
例えば、カラオケ店は延べ面積が700㎡以上の場合、消火栓の設置が義務化します。
詳細は長くなるので割愛しますが、地下や無窓階、4階以上の階はその他の階より消火活動が困難なため、基準が引き上げられているんです。
先程のカラオケ店に地下があったり、4階以上の階があったりする場合は、該当階の床面積が150㎡以上のときに消火栓の設置が必須です。
このように大きな建物では消火栓の設置基準が大幅に厳しくなり、コストもかかります。
しかし、倍読み規定と呼ばれる設置基準の緩和もあり、防火対象物の構造を準耐火構造や耐火構造にすることで、基準面積を2倍~3倍に緩和することができます。
通常、地下のあるカラオケ店は地下の面積が150㎡以上のときに消火栓の設置義務が発生しますが、耐火構造のカラオケ店の場合、地下の面積が450㎡以上になるまで消火栓の設置義務はありません。
新しく設置する場合はどの基準で考えればよいか、少し複雑ですので注意してください。
屋外消火栓の場合
屋外消火栓は屋内型と比較すると簡素です。
これは屋外消火栓の使用用途が、建築物の1階と2階の消火活動だけを想定しているから。
とは言ってもしっかりとした基準がありますので、新しく設置する場合は以下の点に注意しましょう。
・半径40mの円で建物各部を覆うことが出来るように配置。
・ホース格納箱を消火栓から歩行距離5m以内に設置。
・消火活動や避難活動に支障のない位置に配置。
・配管・消火栓の腐食・凍結の防止に留意すること。
4. まとめ
今回はたくさんある消火栓の種類とその構造、使用方法までご紹介してきました。
実際に設置をするのは屋内型のほうが多いかもしれませんが、だからこそ屋外型消火栓についてもよく知っておく必要があります。
また、実際に使用する場合にも注意が必要です。
火災現場に出くわさないのが一番かもしれませんが、何があるか分かりません。
消火栓の使用方法もしっかりと覚えておいて有事に備えてきましょう。
消防設備点検なら全国消防点検.comまで

全国消防点検.comでは消防設備点検のご相談を承っております。
「古い建物でいつ設置されたものかわからない・・・」
「消防設備についてよくわからないし、点検もしているのかな?」
などなど、些細なことでもご相談を承っております。
消防点検に限らず、様々な設置や点検等も承っており、
依頼する業者をまとめたい、点検類をまとめて依頼したいなど幅広くご相談が可能です
まずはご相談だけでも大歓迎です!
どうぞお気軽にお問い合わせください。


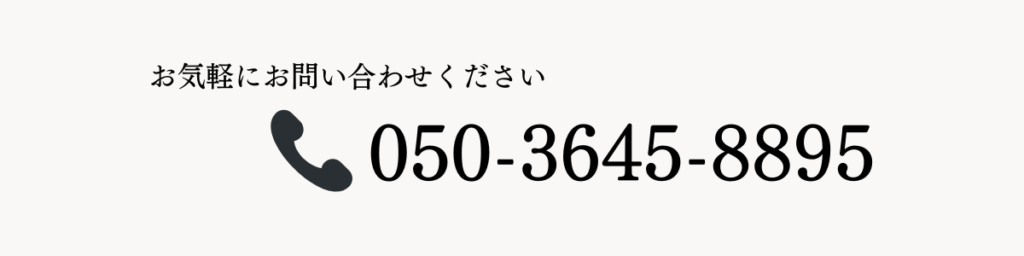

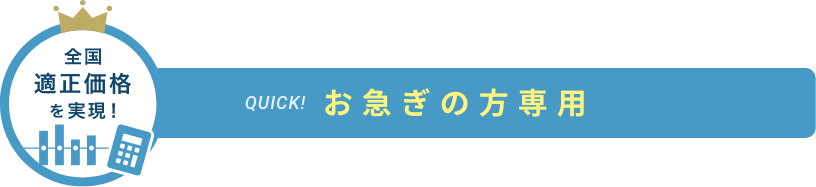

 火災報知器にカバーを付けなくても良い場合
火災報知器にカバーを付けなくても良い場合