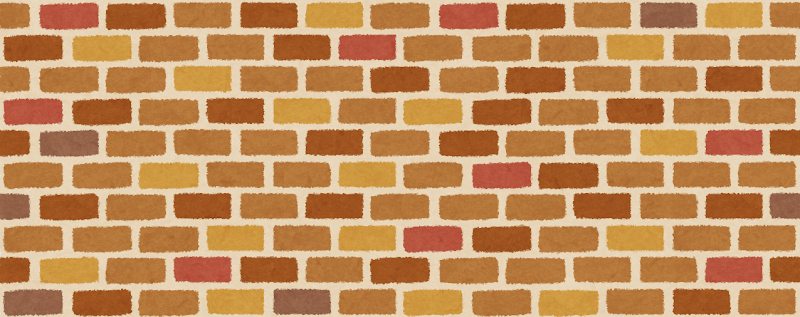お役立ち情報
2019.07.05
耐火構造とは?
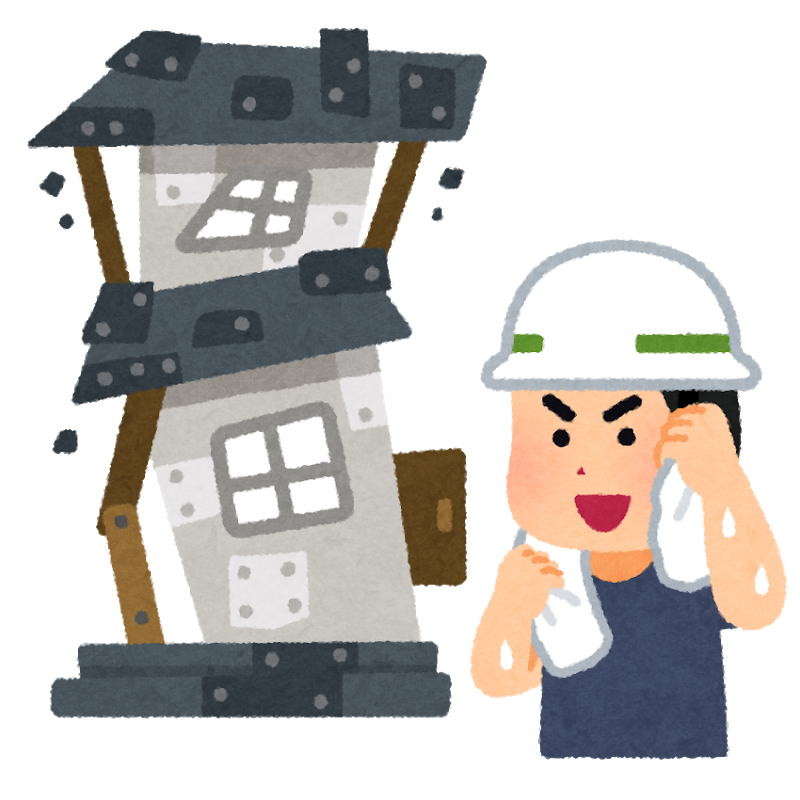
こんにちは!日本全国の消防点検・施工を行っております、全国消防点検.comです!
万が一の火災時に被害を抑えるよう、法律で建物の構造や用いるべき材料などが決められています。特に共同住宅や商業地域にある住宅などには、高いレベルの技術的基準が設定されています。その主なものが、「耐火構造」、「準耐火構造」、「防火構造」の三つの構造。階数や延床面積、用途のほか、建設地が防火地域か準防火地域かで区分が決まります。
今回は「耐火構造・耐火建築物」がテーマです。
消防設備士の試験に関係する事柄でもあります。
それでは一緒に勉強していきましょう!
【目次】
1. 火災を考える場合の建築物の造り―耐火構造・準耐火構造
2. 福祉施設に該当する施設とは
1. 火災を考える場合の建築物の造り―耐火構造・準耐火構造
耐火構造・準耐火構造とは、延焼させないことはもとより、火事になっても一定時間は構造体力が低下しないことを要求された構造のことです。この一定時間とは耐火時間ともいい、部位別に30分~3時間は構造体力が低下しないということです。火災が鎮火するまでの間、最長3時間の倒壊を防止する「非損傷性」、最長1時間の火災による熱で類焼しない「遮熱性」が求められます。
耐火構造・準耐火構造は建築基準法に規定されているものです。そのため、屋外からの延焼を防ぐことが目的の防火構造よりも、厳しい基準となっています。
防火対象物でも同じようなことが言えますが、消防法はもちろんのこと、消防設備と建築基準法が密接に関係していることがわかりますね。
この耐火構造とは具体的に言えば、壁、柱、床など主要構造部について、政令で定めた耐火性能基準に適合する、鉄筋コンクリート造、れんが造などの構造のことです。
詳しく言うならば、
①国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは、②国土交通大臣の認定を受けたものを言います。
木造や鉄鋼構造等には耐火構造には及ばないものの、火災に強い、準耐火構造としての基準が設けられています。
それでは耐火構造の建物について詳しく見ていきましょう!
2. 火災発生時に一定時間構造体力を維持する建築物
―耐火建築物・準耐火建築物
耐火建築物とは、主要構造部と外壁の開口部において、以下の項目に適合する建築物をいいます。なお、主要構造部とは、「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻りの舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの」(建基法2条1項5号)をいいます。
①主要構造部が以下のイ、ロのいずれかに該当すること
イ.耐火構造であること ロ.政令で定める技術的基準に適合すること
②外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他防火設備を設けたもの、またはそれ以外の建築物で、同等の準耐火性能を持つもの(外壁耐火構造でロ準耐1号と呼ぶものと主要構造部を不燃材料で造ったロ準耐1号と呼ぶものと主要構造部を不燃材料で造ったロ準耐2号と呼ぶものの、3つの種類がある)で、外壁の延焼のおそれのある部分に耐火建築物で規定した防火設備を設けたものをいいます。
もう少しくだいてみていきましょう。
延焼のおそれのある部分は、建築基準法において、火災に関係した条文として初めに登場する用語です。火災が発生し、その火災が隣接する建築物などに延焼し、広がっていくおそれのある部分という意味です。
部分の特定は、ある基点(前面道路の中心線、隣地境界線、同一敷地内にある2棟以上の建物で延べ面積500㎡を超える場合の、向かい合う外壁の中心線)からの一定の水平距離内に入る壁、屋根などを指します。ざっくり言えば建物と建物の間の境界線のこと。
基点からの水平距離は、1階にあっては3m以下、2階以上は5m以下をいいます。炎の上に広がる性質から1階より2階のほうが厳しくなっています。壁に関しては、間仕切り壁とは、建物内部の部屋と部屋とを区切るための壁です。耐力壁は、建物を支える役割をもつ壁のことを指します。しかし、防火上有効な公園、広場、川などの空地や水面、または耐火構造の壁などに面するものは除外されます。
耐火性能とは、建築基準法などにおいて、火災が鎮火するまでの間、火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために、建物の耐力壁や間仕切り壁・外壁・柱・床・梁などに求めている性能のことです。
防火対象物の主要構造物が耐火構造で、かつ内装仕上げが難燃材料であることで、設置しなければいけない消火器の数を減らすことができるんです。
必要な消火器の本数を出す計算では、面積を算定基準面積で割った数と消火器の能力単位を合わせます。また、小型消火器の場合、消火器までの歩行距離を20m以下にするように配置を決めます。
例えば図書館の場合、300㎡以上の面積の場合に消火器を設置しなければならず、算定基準面積は200㎡になります。しかしながら主要構造部が耐火構造で内装仕上げが難燃材料であれば、算定基準面積は2倍の400㎡になるのです。
防火構造と同じように、火災の被害を最小限に抑えるために法律で定められた構造がほかにもあります。防火性能の高い順に「耐火構造」「準耐火構造」「防火構造」となっており、建物の階数や延床面積、用途、所在地が「防火地域」か「準防火地域」かによって、それぞれの構造に区分されます。防火構造だけを重視していると短時間で周囲に燃え広がったり、建物が短時間で倒壊してしまったりする恐れがあります。


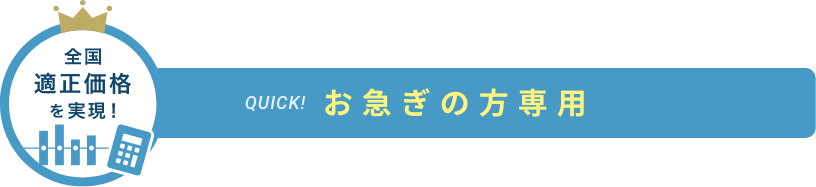

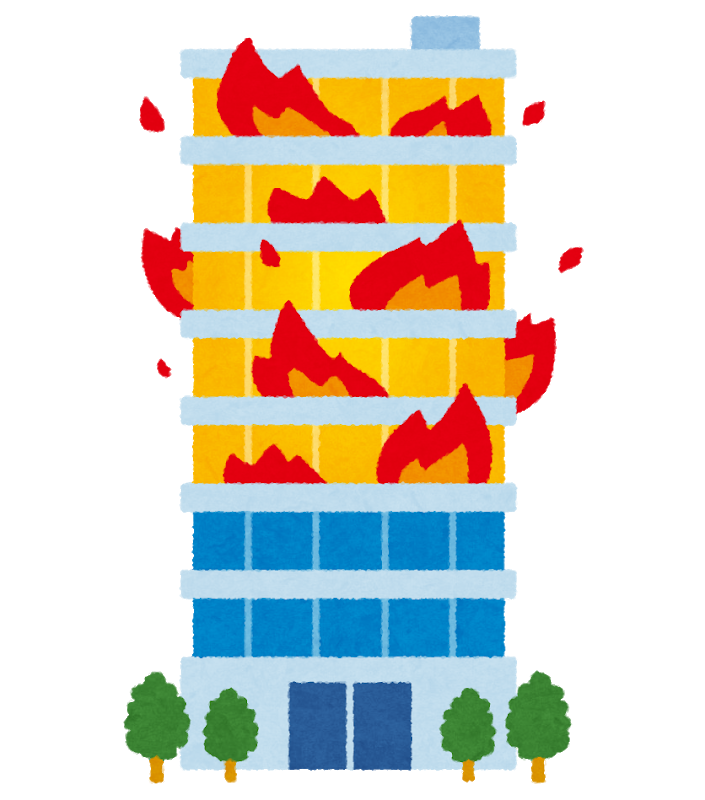 防火管理者になるには?
防火管理者になるには?